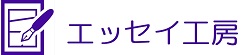「運のいいことに」を受ける言葉はどこに?
「運のいいことに、能登で地震があった」
先日、このような発言をした政治家がいました。受け入れられないと、厳しい批判が相次ぎました。
この発言だけを聞くと、「何ということを言うのだ!」と怒りが収まりません。けれども、その政治家は本当にそう思って発言したのでしょうか。
私はそのニュースを聞いて、「運のいいことに」という修飾語を受ける言葉が、離れたところにあるために、誤解が生じたのだと思いました。
エッセイにおいても、修飾する言葉の位置によって、誤解を招いたり、意味がうまく伝わらなかったりします。その場合は、修飾する言葉を、修飾を受ける言葉の近くに持っていくと、たいていは解決します。
例)赤い帽子をかぶった子どもを抱いている女性
赤い帽子をかぶっているのは、子どもか、女性か。自然に読むと、子どもが赤い帽子をかぶっているように受け取れます。女性がかぶっている場合は、赤い帽子と女性を近づけて、「子どもを抱いている、赤い帽子をかぶった女性」とすると誤解は生じません。
例)私は泣きながら別れを告げる彼女を見つめていた
泣いているのは、私か、彼女か。
私が泣いているのなら、「別れを告げる彼女を、私は泣きながら見つめていた」
彼女が泣いているのであれば、「泣きながら別れを告げる彼女を、私は見つめていた」
とします。「泣きながら」という言葉を、その動作の主語の近くに持っていけば、あいまいさがなくなります。
冒頭の「運のいいことに」も、
例)運のいいことに、大きな地震があったが、誰もケガをしなかった。
→大きな地震があったが、運のいいことに、誰もケガをしなかった。
とすれば、言いたいことが誤解なく伝わるはずです。
そう思いながら、政治家の「運がいいことに」前後のスピーチを調べてみました。以下に、 朝日新聞のサイトから 引用させていただきました。
この議員さんは、二地域居住という制度を推し進めているそうで、それに関する話の途中での発言です。
「……時にはふるさとのことを振り返りながら帰ってこられる、自分の人生でゴールにすると考えられる。そんな仕組みをつくるべきじゃないかと思って、二地域に居住できるようにしている。総務省は普通、こういう時には立ちはだかって反対をするんですが、今回に至っては本当に協力的でした。むしろ率先してやられている。
また運のいいことに、能登で地震があったでしょ。能登で地震があった時に、輪島だとか、北の方。その地域には、寸断された道をずっと歩いて2時間半とか3時間かかるんです。 被災者は金沢に住んで、いちいち自分の被災した家を点検しにいくような作業を、ずっとしておられたわけですね。輪島市の市役所もないのに、金沢市に住んで、新しい被災事業のための補助金をもらうのに、自分は住民票をいちいち、市役所がまともに動いてもいないところで、おかしいじゃないというような話で。
結局、緊急避難的ですけど、金沢にいても輪島の住民票が取れるようになっていったんですよ。やればできるじゃないかと私は思いました。チャンスです。だから、二つの地域で住民票登録できるんだ。……」
どこまで読んでいっても、「運のいいことに」という修飾を受ける言葉が見つかりません。強いて言えば、「金沢にいても輪島の住民票が取れるようになっていったんですよ」につながるのでしょうか。あまりに離れすぎ、しかも「運のいいことに」という言葉がこの内容に合うのかどうか。これでは、批判を受けても仕方ないように感じました。