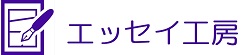茶柱の立つところ
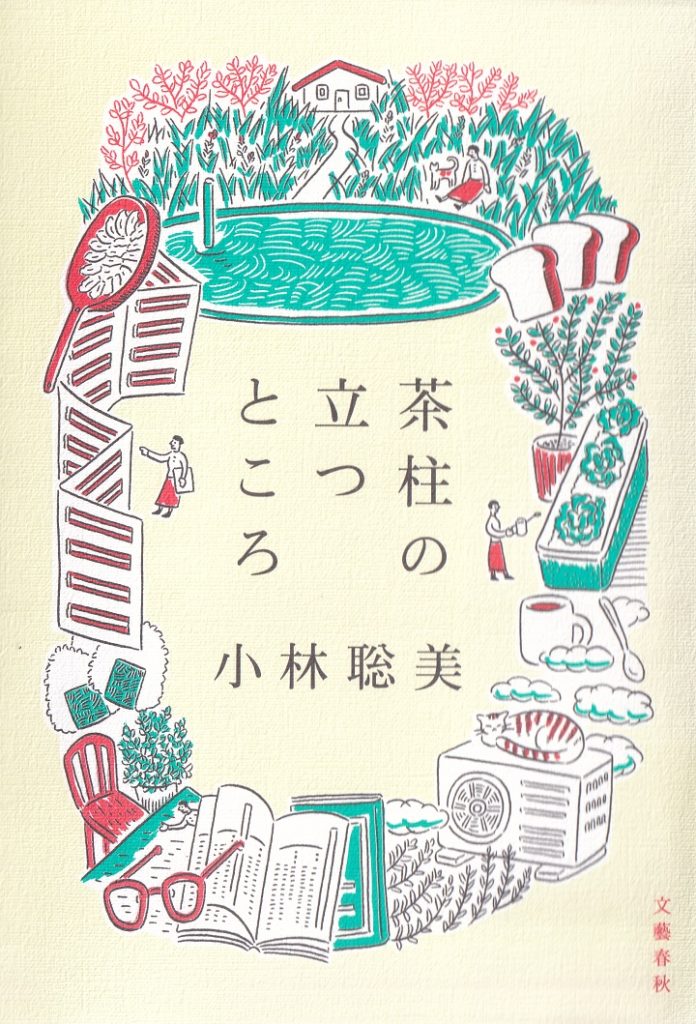
『茶柱の立つところ』(小林聡美著 文藝春秋 2024年3月)をご紹介します。
小林聡美さんが俳優として活躍しているのをご存じの方も多いと思います。最近ではNHKで放映されたドラマ『団地の2人』を私は楽しみました。落ち着いた雰囲気もあり、ユニークでおちゃめな部分もある。そんな方のようにお見受けしています。
書店の棚で、名前を見つけてふと手に取ってみました。いわゆるタレント本とは違って、文字の量がしっかりあり、少し読んでみると、文章もお人柄どおり落ち着いていて、しかも読みやすい。装丁も気に入って、読んでみることにしました。
これは後で気づいたことですが、本書の装丁は鈴木千佳子さんという方によるもので、前回ご紹介した『星になっても』の装丁もこの方でした。意識せず、私の好きな装丁に手が伸びていたのかもしれません。
小林さんのエッセイには、俳優だから経験するというような特別な話はほとんど登場しません。一生活者として暮らしのなかで感じたこと、五十代後半になって見えてきたこと、新しい習い事など、誰の周りにも起こりそうなことが、ていねいに、小林さんならではの切り口で描かれています。
この「小林さんならではの切り口」が独創的でおもしろい。
本書の最初のエッセイ「思い込み」は、フライパンを変えたところ、餃子がうまく焼けなくなったという話です。あらすじとしてはこれだけで終わってしまう話を、5ページにわたる文章に仕上げています。冗長なわけではなく、以前のフライパンではどうだったか、フライパンに餃子の底がくっついた惨状を見て平野レミさんの「食べれば焼き餃子」を思い出す、うまく焼けないことによる自信喪失、失敗するという思い込みがいけないのではないかなど、次々と展開して、読み手をぐいぐい引っ張っていきます。
1泊2日のバスツアーで中山道宿場町見物と自然林散策に行ったときのエッセイは、遠足のおやつセットをとバスガイドという仕事のすごさについての話がほぼ9割を占めていました。これまた語り方がじょうずで一気に読ませてしまうのでした。
小林さんが生活のなかで気づくポイントには、「そうそう」と共感できるものが多く、今後の自分自身のエッセイに発展しそうなネタをいくつも見つけました。
健康に気をつけるために運動や食事を気にかけても、年はとるし、病気にもなる。物を大切に使い続けようと心がけていると、くたびれたものに囲まれた生活になってしまう。同じ遺伝子をもつおじさんやおばさんが、年をとるにつれておんなじ顔になっていった。年齢を重ねていくにつれて自分の着たい服が見つからなくなり、デパートの雰囲気にのみ込まれてつい高い物を買ってしまった。
自分に引き寄せて、 何か書けそうではありませんか。
本書のタイトル『茶柱の立つところ』は、エッセイのタイトルとしては登場せず、「あとがき」に「湯呑に茶柱が立ってるのを発見した時の驚きは、おそらくいくつになっても新鮮で、嬉しい。……私の、そして皆さんのありきたりな日々のどこかに、ときどき茶柱が立ちますように」と書かれていました。
小林さんは タイトルを通じて、読者と自分自身に「生活を楽しみましょう」と伝えているように感じました。