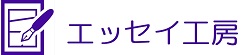合同合評会プロジェクト(その3)
11月29日開催予定の合同合評会が、だんだんと迫ってきました。
合同合評会とは、私が関わっている5つのエッセイ教室の参加者が、教室の枠を超えて一堂に会し、みんなで合評をするというプロジェクトです(その1、その2に経緯が書かれていますので、ご覧ください)。
作品は17篇集まり、合評だけ参加したいという1名をプラスして、18名の参加です。
毎月、教室のあとに、有志による実行委員会が打ち合わせを重ねています。
合同合評会を催すにあたり必要なことは何か。会計、タイムキーパー、名札準備、会場への誘導、ホワイトボードに当日のスケジュールを書くなど、やるべきことを列挙し、みんなで分担。エッセイ教室は、社会経験の豊かな、しかもさまざまな経験をしている面々の集まりですから、どんどん決まっていきます。
今回の合評会の一番の問題は、3時間という限られた時間で、17篇の合評を終えるためにはどうしたらよいか、です。始まりと終わりの言葉は極力短くするとしてもトイレ休憩は必要なので、それらを考慮すると、1作品9分以内で終わらせる必要がありそうです。時間節約のため、1作品に対して3人の合評者を前もって決めておき、1分以内で意見を言ってもらいます。書き手本人による作品朗読は、考慮の末、行うことにしました。
となると、朗読が3分半~4分、3人の意見3分、講師の私が2分でまとめて、次の作品へ、という流れで進めていくことになります。私を含め意見が少しずつ長引いて進行が遅れると、あとの作品の持ち時間に影響が及ぶおそれがあります。
「1分で発言できる分量は、息継ぎを考えると250字程度です」と、実行委員の中に専門家がいてアドバイスがありました。
「実行委員は、当日、誰かの指示を待たずに、気づいたことを行動に移しましょう」
という声も上がって、準備や運営にはまったく心配ありません。
私は9分以内で次の作品に進めることに専念します。