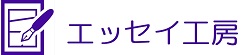エッセイに登場する「私」
先日のエッセイ教室に提出された作品では、「私」と「さっちゃん」の2人が主人公でした。最初の部分のあらすじを紹介します。
すてきな女将に魅かれて、私はそこの料亭で働き出した。その女将の娘さっちゃんはまだ小さく、忙しい母親にかまってもらえないため、しょっちゅう泣いていた。私は自分から志願して、さっちゃんの面倒をみる「おねえちゃん」になった……。
その後、私が料亭を去るまでの7年間が描かれます。なかなか経験できない話で、まるで小説を読んでいるようでした。また文章自体も魅力的で、読み手を引き付ける作品でした。
作品の最後の部分には1行開けがあり、文中の「私」はさっちゃんの面倒をみる「おねえちゃん」のことで、「さっちゃん」が筆者本人であると書かれていました。
エッセイのなかに「私」と書いてあれば、それは筆者本人をさすことが多い。いえ、ほぼ100%、筆者本人のことです。読み手はそう思って、作品を読み進めます。
それが、この作品において、「私」は筆者ではなかった。「さっちゃん」が筆者。ええ? 最初は驚き少々混乱しましたが、そうとわかって読めば、問題はまったくありませんでした。
筆者に、このように書いた理由を聞くと、
「おねえちゃん」と「さっちゃん」の関係は少々複雑で、「さっちゃん」を「私」として書くと、まどろっこしい説明がたくさん出てきて、それこそ、読者に伝わらなくなる。なので、変則的とは思ったけれど、「おねえちゃん」を「私」として書いてみました。
ということでした。
これまで、エッセイの文中に出てくる「私」が筆者本人ではない作品を読んだ記憶はありません。ですので、最初は驚きましたが、この書き方が本作品にはしっくりくると感じました。また、筆者がおねえちゃんのことをよく知っていて理解しているので、おねえちゃんの身になり替わって「私」という立場で書くことができたのでしょう。誰もがそういう書き方をできるわけではないとは思いました。
この作品で一番重要なポイントは、「私」と「さっちゃん」が誰のことを指しているのか、筆者が作品内で明らかにしてくれたことです。だからこそ、読み手も、この作品を受けとめることができ、かつ作品の世界に入り込んで楽しむことができたのだと思います。