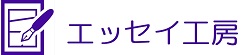この言葉を使ってもいいですか
ある言葉について、今回は考えたいと思います。 エッセイ教室で合評した作品に書かれていた言葉です。
筆者がケガしたとき、滴り落ちる血の鮮やかな赤い色を見て感じたことを、以下のように綴りました。
「リストカットをする人の気持ちが分かったような気がしたが、その考えはすぐに消え去った」
このエッセイについての合評で、次のようなやり取りが続きました。
質問者「自殺する人の気持ちが分かった、というのはどういうことですか?」
筆者「リストカットは、自殺とは違うんですよ。自分を傷つける行為で、血を見て生きていることを確認してるのです」
質問者「そうなのですか。まったく知りませんでした。リストカットは自殺の手段だと思っていました。でも、もしこれをリストカットする子どもを持つ親御さんが読んだら、どう思うでしょうか」
筆者「だから、すぐに消え去ったと書いたのですが」
質問者「そう書いてあっても、リストカットという言葉を使うこと自体、どうなんでしょうか」
このやり取りの中に、問題は2つあると思います。
1)「リストカット」に対する認識が、筆者と読み手とでは大きく乖離していた
筆者以外は、リストカットは自殺するための行為と思っていました。ですから、文中に「リストカット」の文字が現れた時の受け止め方が、書き手の気持ちとはまったく違っていました。この言葉のさす行為が、どこまで一般に知られているかについて、書き手は注意を払う必要がありました。こう書いている私自身、おおまかな知識しかありませんでした。
2)このエッセイに「リストカット」という言葉を使う必要があったか
使ってはいけない言葉だとは思いませんが、センシティブな言葉であるのは確かです。筆者もそれを感じているからこそ、エッセイに「その考えはすぐに消え去った」と書いたのです。ほかの言葉で、血の赤さを表せなかったのか。表現方法をいろいろ考えた結果、やはり「リストカット」を登場させたいのなら、あとは書き手の判断に任せるしかありません。
私は、「この言葉を使ってはいけない」という決まりは、なるべく作りたくないと思っています。差別語についてはもちろん論外ですが。どういう言葉も話題も、エッセイに登場していいはずです。ただ、それは「書き手が書きたいのなら、何でも書いていい」ということではありません。読み手がいる「エッセイ」という形をとるのですから、読み手がどう受け取るか、読み手にそのことがきちんと伝わるのかを、考えなければならないと思います。
今回はエッセイ教室の中だけで読み合う作品でしたが、ほかの人にも読まれる場に出す場合、「リストカット」と書いていいのでしょうか。
そういう質問も出ました。
上記の2つの問題点をクリアしたのであれば、イエスと答えたい、というのが私の考えです。